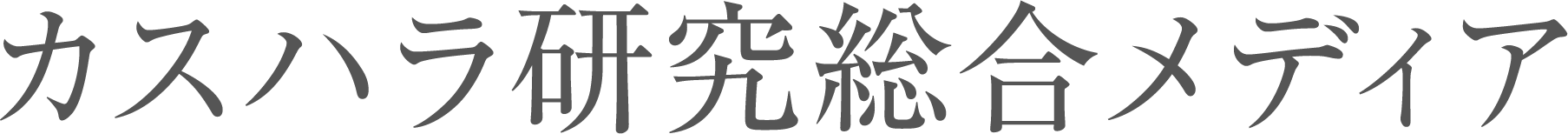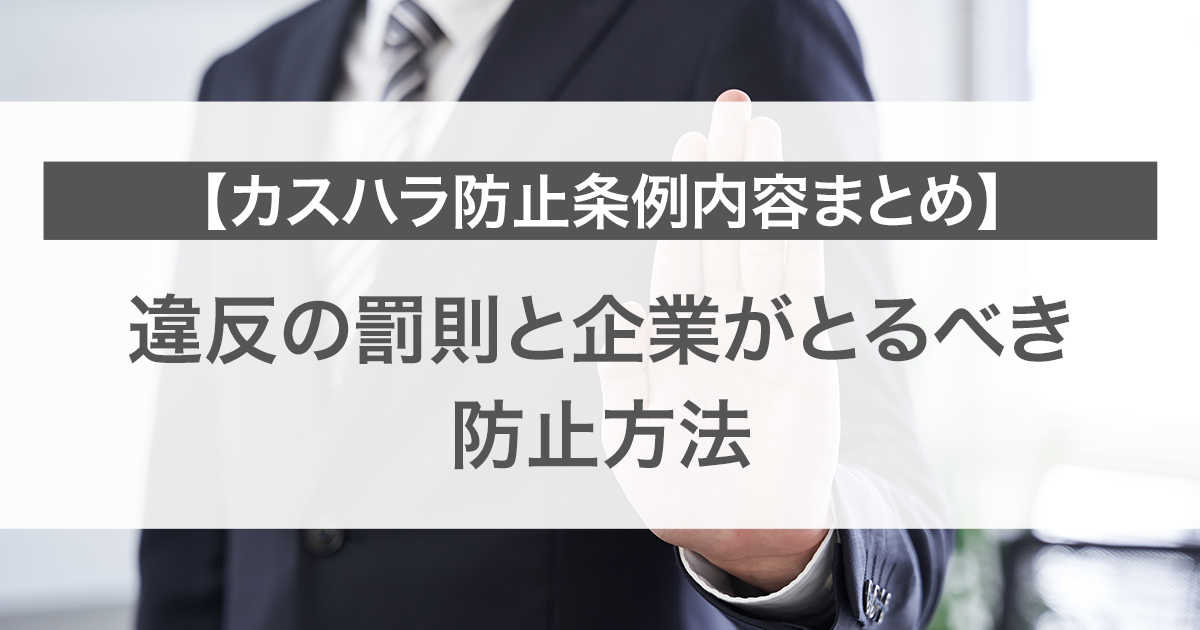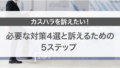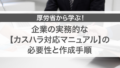企業と顧客、自治体が協力してカスハラ防止社会の実現を目指しましょう!
・ カスハラを防止するための条例について、詳細な内容を知りたい!
・ カスハラ防止条例が企業にもたらす影響と期待される効果を知りたい!
・ カスハラ防止条例に反した場合の罰則について知りたい。
・ その他、カスハラを防止する方法全般を知りたい!
このように、本記事では「カスハラ防止方法」とそれに関連する条例に焦点を当て、その内容や罰則、企業がとるべき防止策について詳しく解説しています。
昨今、カスハラ(カスタマーハラスメント)の問題が深刻化しています。
顧客からの過剰な要求や嫌がらせにより、従業員が精神的・身体的に追い詰められるケースが増加しているためです。
企業としての適切な対応が早急に求められている状況となるため、何をすべきかを明確にしていきましょう。
カスハラについて
カスハラとは、顧客による不当な要求や暴言を指し、従業員が精神的・身体的に追い詰められる問題を指しています。これは、あらゆる業種において職場環境の悪化や退職者の増加を招いている傾向にあります。
まずは、カスハラを防止するための条例や、それに伴って変化している社会の現状について詳しく解説します。
カスハラ防止の条例とは
カスハラの防止方法の一つとして『カスハラ防止条例』があります。
従業員が顧客からの不当な要求や暴言などのハラスメント行為から保護されることを目的とした法律・条例です。
主に自治体レベルで制定されており、誰かを罰するためではなく、職場環境の改善や従業員の安全確保を目指しています。
カスハラという社会問題の防止を企業だけに任せるのではなく、自治体としても見過ごさないという姿勢が伺えます。
例えば、東京都の「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が注目を集めています。2024年10月4日に東京都議会が可決・成立させました。この取り組みは全国初であり、2025年4月1日から施行される予定です。
この条例は、企業や自治体が協力してカスハラの根絶を目指すための基盤を提供していくことでしょう。
カスハラによる被害の現状
現在、多くの企業がカスハラによる被害を受けています。この問題は年々増加傾向にあり、企業の経営や従業員の健康に対して、以下のような深刻な影響を及ぼしています。
- 従業員の精神的ストレスの増加
- 退職者の増加
- 業務効率の低下
特にサービス業や小売業、医療・介護分野での被害が顕著です。
これにより、企業としての信用に以下のような影響が及ぶ可能性があります。
①顧客からの信頼低下
ネガティブな口コミや評判が広がり、顧客数の減少を招く可能性があります。
②投資家や取引先の懸念
取引先や投資家からの信用が低下し、事業継続が困難になるリスクが考えられます。
③地域社会における評判の悪化
地域社会からの支援や協力を得にくくなる場合が考えられます。
カスハラを放置した場合、これらは悪循環を生み、企業と従業員を疲弊させていきます。その場しのぎの対応や、時間任せな解決方法はありません。
これまでは厚生労働省がカスハラ対応マニュアルを作成し、啓発活動を行ったりと、主体的な動きをみせていました。現在は、東京都の他一部の自治体で条例が制定され始めています。
企業のみの力では従業員を十分に守ることができない場合もあり、国としても放置すべきでない社会問題であると判断した結果が条例の制定です。
まずは企業がアクションを起こしましょう!
自治体の条例を味方につけ、カスハラを防止する方法を構築してください。
カスハラ防止条例は東京都・北海道で制定
現在、注目されているのは東京都と北海道です。
東京都では、2024年に「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が制定されました。この条例は、カスハラの認知度向上と防止対策の強化を目的としています。
また、北海道でも同様に、2024年11月26日にカスハラ防止条例の制定が可決されました。東京都に次いで2例目となります。
さらに愛知県も条例制定を検討中とのことで、その他の府県もあとに続くといった全国的な広がりを見せています。
次の章では、東京都のカスハラ防止条例の具体的な内容や取り組みについて詳しく解説します。
東京都カスハラ防止条例の内容
東京都が制定したカスハラ防止条例は、従業員を守るための具体的な施策を示す重要な取り組みとなっています。その条例の概要や普及啓発の事例を通じて、実際の効果や活用方法を学びましょう。
東京都のカスハラ防止条例の概要
カスハラ防止のためにこの条例が制定された背景には、近年のサービス業や小売業を中心に従業員への暴言や過剰な要求がエスカレートし、その結果、職場環境の悪化や従業員の退職、精神的な不調への波及するという事例が深刻化していることが起因します。
これを放置すれば社会的信頼の低下や経済的損失に繋がることが懸念されます。そのため、都は具体的なルールを設け、職場の健全化と従業員の安全を確保することを目指す環境づくりを始めました。
東京都のカスハラ防止条例では、大まかに以下のような項目が定められています。
- カスハラの定義と範囲の明確化
- 企業や自治体による啓発活動の責務
- 従業員の保護を目的とした措置の推進
カスハラの具体的な防止策の検討が推奨され、企業に対する対応指針が明確化されました。これらの取り組みの先に従業員が安心して働ける環境整備と、顧客との良好な関係を築く未来が期待されています。
普及啓発ポスター事例
東京都では普及啓発の一環として、職場や公共施設で使用できるポスターを配布しています。これらのポスターには、カスハラの防止に関するメッセージやイラストが採用されており、誰でも一目でわかりやすい内容になっています。
顧客向けポスター
引用:東京都HP「カスハラ防止条例施行普及啓発ポスターを作成」
従業員向け
引用:東京都HP「カスハラ防止条例施行普及啓発ポスターを作成」
ポスターは東京都公式サイトからダウンロード可能です。また、印刷物は自治体の窓口で入手可能のようです。
東京都のポスターは「顧客等向け」と「従業員向け」を用意している点が特徴ですね。
一方で、厚労省が提供するポスターは東京都のポスターとは異なる特徴があります。厚労省のポスターは全国規模での事業者・就業者・顧客の意識向上を目的としており、包括的なメッセージが強い印象を受けます。
引用:厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!」
下図の様に任意のイラストをはめ込むことができる様式も用意してくれています。
引用:厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!」
これなら自社の事業に適した内容のポスターに仕上げることができます。
厚労省のポスターは、厚生労働省公式サイトからダウンロード可能です。
カスハラ防止『条例』の重要性
上記では、東京都を参考にカスハラ防止条例の内容をお伝えしました。
次は、カスハラ防止『条例』がどの様に従業員の保護や企業の信頼維持という効果に繋がるのかについて焦点を当てていきます。
『条例』がなぜ必要なのか、そしてその重要性について解説します。
なぜカスハラ防止が必要なのか
まず、カスハラが放置されるとどの様な問題が発生するのでしょうか。
下記に企業と従業員、それぞれのリスクを簡潔にまとめます。
企業としてのリスク
- ブランドイメージの低下
- 訴訟リスクの増加
従業員(個人)のリスク
- メンタルヘルスの悪化
- 職場離脱による人材不足
カスハラを防止することは、従業員の保護や企業の健全な成長に不可欠です。
カスハラ防止策を講じることで従業員の安心感が向上し、職場環境が整備されるとともに、企業の社会的信用も高まります。
こうした背景から、自治体がカスハラ防止条例を策定し、それに基づいて企業が具体的な防止策を講じるという動きが加速しています。
次は、このような条例の重要性についてさらに詳しく解説します。
カスハラ防止条例の重要性
前述したとおり、カスハラ防止条例は企業が従業員を保護し、職場環境の改善を促進させるために不可欠な取り組みです。
企業のカスハラ対応と条例が掛け合う事でもたらす効果については下記のとおりです。
カスハラが引き起こす問題
SNSの普及に伴い、カスハラの被害が共有されるケースが増えました。それに伴って、従業員への暴言や過剰な要求が社会問題として顕在化してきました。
・精神的ストレスが原因で業務が滞る
・理不尽なクレームにより従業員の健全な生活が脅かされる
このような被害は従業員の離職を触発し、企業の信用低下や運営リスクを高め、経営に深刻な打撃を与える可能性があります。
従業員保護と職場環境の改善が見込める
カスハラ防止の『条例』は意識改革の促進が目標ですが、カスハラを防止することで、従業員の保護と職場環境の改善を見込むことができます。
カスハラ防止に努めている企業が増えつつありますが、中には未だ踏み出せていない企業も多く存在しています。
「自社はまだカスハラ被害による影響がないから大丈夫」と思っていませんか?
企業が対応に遅れをとっている間に、従業員の心身の健全さが損なわれる可能性があります。従業員が傷ついてから、ようやくカスハラ防止を意識して対応していては遅いのです!
『条例』は健全な社会風土の醸成を促進することが目的です。
条例に基づいたカスハラ防止は従業員の保護と職場環境の改善に直結し、下記のような効果を期待することができます。
従業員の保護
①心理的ストレスの軽減
カスハラを受けた場合の対応策が明確になり、従業員が不安やプレッシャーを抱くこと可能性が少なくなります。また、メンタルヘルスの問題を予防し、十分なケアを施すことが期待できます。
②安心して働ける環境の提供
条例による明確なルールの存在によって、従業員は会社が自身を守ってくれるという安心感を持つことができます。そして、有事の際のサポート体制が整備され、適切な対応が可能となります。
③従業員の定着率向上
カスハラ防止対策を徹底する企業は「従業員を大切にする会社」と認識され、離職率の低下を防ぐ可能性が高くなり、結果として、人材不足解消にも寄与することが期待できます。
職場環境の改善
①職場全体のモラル向上
カスハラ防止条例によって企業の基本方針が定まることで、従業員同士が協力して問題に立ち向かう意識が醸成されます。その結果、カスハラに対する毅然とした対応の育成を促進し、職場全体の士気向上に繋がります。
②業務効率の向上
不必要なトラブル対応やストレスによる生産性の低下が抑制され、日々の業務に集中できるようになります。
③企業イメージの向上
カスハラ対策に取り組む企業は、社会的に「労働環境を重視している企業」として評価され、信頼性の向上が期待できます。その結果、消費者や取引先からの信頼感も高まり、企業全体の成長に寄与します。
条例は企業のカスハラ防止方法の構築を加速させ、カスハラに対して毅然と対応し、決して屈しない!という姿勢を育てます。それが最終的に従業員の権利・生活を守ること、そして企業の更なる発展を望むことができます。
また、『条例』は顧客に対する効果的なアプローチの一つでもあります。
カスハラは社会的に許してはいけないモノ。あってはならないコト。
という意識を顧客に与え、間接的にカスハラ防止を果たしています。
条例に基づく取り組みや意識改革の実現という実績の積み重ねがカスハラ撲滅へと繋がります。
カスハラ防止条例の罰則
カスハラ防止条例を遵守しているという事実が企業や個人の信頼を守る鍵です。しかし、基本的には罰則はありません。
ここでは、企業や一般人が条例違反しても罰則がないという点について解説します。
カスハラ防止条例の遵守について
カスハラ防止条例とは、顧客からの不当な要求や暴言などのハラスメント行為を防止するために制定された法律・条例です。
この条例には、従業員を保護するための具体的な指針や取り組みが定められています。
企業にとって条例を遵守するということは、従業員の安全を守るだけでなく、社会的信用を維持する重要な義務なのです。
条例違反に罰則は?
条例の遵守を促したいところですが、違反しても罰則はありません。カスハラという行為を認めない・禁止するという解釈までが条例の範囲となっています。
では、罰則がなくてもカスハラ防止条例の遵守に結びつくのでしょうか?
企業への条例違反について
企業が条例を無視・違反した場合、罰則はありませんが下記のようなリスクの可能性はあります。ご注意ください!
- 行政指導の実施
行政機関からの厳重な指導が行われ、改善計画の提出を求められることがあります。 - 社会的信用の喪失
条例違反が公に知られた場合、企業のブランドイメージが大きく損なわれる恐れがあります。 - 取引停止や契約解除
取引先や顧客からの信頼を失い、ビジネス関係が断たれる可能性があります。 - 従業員の離職率増加
従業員が不安を感じ、退職が相次ぐことで業務運営に支障をきたす恐れがあります。
一般人への条例違反について
顧客がカスハラ行為を行った場合についてです。
企業同様、罰則はありませんが下記のようなリスクや処置が検討される可能性があります。
- 警告の発行
自治体や企業から正式な警告が行われることがあります。 - 出入り禁止措置
問題行動が繰り返される場合、顧客が店舗や施設に出入りできなくなることがあります。 - 民事訴訟の可能性
従業員や企業が被害を受けた場合、損害賠償を求めて法的措置を取る場合があります。 - 警察への通報
暴力行為や脅迫が伴う場合には、警察が介入し、刑事責任が追及される可能性があります。 - 社会的信用の喪失
行為が公開されることで、個人としての評判が大きく損なわれるリスクがあります。
『条例』の違反は、企業や個人にとって取り返しのつかない結果を招く場合もあります。罰則の有無に関わらず、社会的信用や信頼を失うことや、長期的な影響を受ける可能性が高くなることを念頭におきましょう。
その間、企業は経営基盤を揺るがされます。個人は日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。
また、カスハラ防止条例は制定され始めたばかりです。今後の社会情勢次第では当然、罰則等の処置が検討されることもあり得ます。願わくば、カスハラという社会問題がこれ以上の被害を生む前に沈静化してほしいものです。
このようなリスクを未然に防ぐためにも、条例を順守し、ハラスメントの根絶に向けた日常的なカスハラ防止方法を追及しましょう。
企業がとるべきカスハラ防止策
企業がカスハラ防止に向けて積極的に取り組むことは、従業員の安全と職場環境の改善に直結すると述べました。その上で『条例』を理解することは不可欠です。
最後にカスハラ防止条例が企業にもたらす影響、それを考慮した防止策の具体例、そして期待される効果について考えてみましょう。
条例が企業にもたらす影響
カスハラ防止に向けて、企業が能動的な取り組みや条例遵守に努める意義について解説します。
能動的なカスハラ防止が大切
カスハラを防止するためには、企業が受け身でいてはいけません!
主体的かつ能動的に取り組むかどうかによって、「従業員の安全と職場環境を守る」という結果が大きく変わってきます。
企業が能動的に取り組むことで、以下の効果が期待されます。
- 職場環境の改善
- 従業員のモチベーション向上
カスハラ防止ポスターの掲示やカスハラ対応マニュアル作成といった視覚化された防止策の実施は、従業員が自信を持って顧客対応に臨むための心の支えとなり、結果的に企業全体の信用と生産性向上にも寄与します。
遵守義務や罰則について
条例を遵守することは企業の社会的責任でもあります。他の条例と同様に、カスハラ防止条例を守ることで企業は従業員の安全を確保し、職場環境の改善を図ることができます。
「カスハラ防止条例を違反した場合の罰則が気になって検索してみた。」という方!
企業はカスハラ防止条例の罰則の心配をするよりも、努めて従業員へのカスハラ研修や社内教育を推進・活性化させることが肝要です!
条例に基づく企業の防止策
カスハラ防止条例に基づく企業の啓発活動や対応マニュアルの整備、具体的な防止事例について紹介します。
まずは、企業がとるべき7つのカスハラ防止策を下記にまとめます。
【企業がとるべき7つのカスハラ対策】
①基本方針の明確化と従業員への周知
②相談窓口の設置
③対応手順やマニュアルを用意
④社内教育、研修の実施
⑤被害を受けた従業員への配慮
⑥再発防止のための事例データの蓄積と分析
⑦外部機関との連携
「カスハラ対策」について、「企業を守るカスハラ対策とは?具体策7つと業界事例や必要性も解説」の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
今回は具体的な防止事例として、とくにオススメしている下記2点の防止方法について紹介します。
・ポスターによる啓発活動の強化
・カスハラ対応マニュアル作成による防止方法
ポスターによる啓発活動の強化
カスハラ防止のポスターを見かけたことがありますか?
前述しましたが、厚労省や各自治体毎に作成しているカスハラ防止ポスターは、従業員や顧客の意識向上を目的とした重要な啓発ツールです。
まずは職場や店舗にポスターを掲示することで、社会問題に対する認識を広げ、行動を改めるきっかけを作りましょう。
企業や公共の場で掲示されたカスハラ防止ポスターを見かけた顧客はどう思うでしょうか?顧客に対して「釘を刺す」予防効果が期待され、不適切な行動を抑制する役割を果たしてくれます。
些細ではありますが、このような啓発活動は結果として、企業全体の信頼性向上や顧客との良好な関係構築に繋がることが期待できます。
カスハラ対応マニュアル作成による防止方法
既に、カスハラ対応マニュアルは作成してありますか?
カスハラ防止方法として対応マニュアルを整備することで、いざという時でも従業員が安心して対応できるという環境を整えることも重要です。
また、ガイドラインやマニュアルという存在は現場での対応を効率化し、混乱を未然に防ぐ役割を果たすものです。
まずは、企業が従業員に具体的な基本方針と行動指針を示しましょう。
そうすることで、カスハラ発生時のリスクを軽減し、迅速な解決を目指すことができます。
条例遵守も大切ですが、なによりも企業が従業員を守る!という気概と姿勢を内外に見せつけること。これが最も優れた防止方法であるといえますね。
「カスハラ対応マニュアル」について、「厚労省から学ぶ!企業の実務的な【カスハラ対応マニュアル】の必要性と作成手順」の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
条例によって期待される防止策の影響
カスハラ防止条例は企業、従業員、そして社会全体に多大な影響をもたらします。条例の存在によって企業と従業員に期待される効果、そしてハラスメント撲滅に向けた社会的な波及効果について解説します。
企業としての期待
ここまで、条例を遵守することで企業は従業員の安全を確保し、顧客との信頼関係を構築すると述べてきました。
社内のコンプライアンス意識が高まることで期待される職場環境の改善効果を簡潔にまとめます。
- 従業員の安全確保
安心して働ける職場を提供することが可能となります。 - 顧客との信頼関係構築
ハラスメントの抑制と顧客満足度の向上が期待できます。 - コンプライアンス意識の向上
社内ルールの徹底を促します。 - 職場環境の改善
健全な労働環境を実現します。 - 企業の信頼性向上
社会的信用と自社ブランドの価値を強化するきっかけとなります。
従業員(個人)への期待
企業の社内規則という枠を超えた『条例』を知ることで従業員の意識はより一層高まります。
従業員は「企業に守られているだけでなく、さらに大きな枠である自治体や国も自分を守ろうとしてくれている。」「自治体が企業に従業員を守るように促してくれている。それならば安心して働くことができる!」と思うことができるのです。
職場全体の風通しが良くなることだけでなく、従業員の心の安定も大切にしなくてはなりません。その結果、下記の改善を期待することができるようになるのです。
- 働きやすい環境の実現
ストレスを軽減し、生産性の向上を促します。 - 精神的な安定の確保
健康的な労働環境を実現します。 - キャリア形成の支援
安定した労働環境において、社員の成長を促進します。 - チームワークの向上
互いに支え合う職場文化を築き上げていきます。 - 離職率の低下
離職率が低くなり、長期的な人材確保に繋がります。
社会全体でのハラスメント撲滅に向けて
企業と従業員、そして自治体がカスハラ防止に努めても、顧客が変わらなくては撲滅に進みません。
カスハラ防止『条例』の強みはここにあります。顧客も条例を意識し、遵守することで、従業員への配慮や理解と責任ある行動が促進され、互いに尊重し合う社会を形成する可能性が高まります。
このような前向きな姿勢が広がれば、社会全体でのハラスメント撲滅が進むだけでなく、様々なサービス利用の安心感も向上します。結果として、顧客も気持ちよくサービスを利用できる社会の実現に寄与するでしょう。
カスハラ防止方法のまとめ
本記事ではカスハラ防止のために、企業、顧客、自治体が連携して取り組むことが重要であると述べました。それぞれの協力体制の構築や、企業主体の行動を通じて社会全体でのハラスメント撲滅を目指しましょう。
企業と顧客、自治体を連携させる防止策
企業、顧客、自治体が相互理解のもとで一体となり、カスハラ防止の取り組みを進めることが重要です。今は未だこうした連携が十分に機能せず、カスハラという社会問題が深刻化しています。
しかし、三者が協力することで従業員の安全が守られ、顧客対応の質が向上するだけでなく、社会全体が健全な姿へとシフトしていく可能性が開けます。
企業主体のカスハラ防止社会の実現
『条例』頼みの姿勢ではいけません!
やはり企業が主体的に行動し、従業員と顧客の双方にとって良好な関係を築く努力が第一に求められます。
まずは企業が『カスハラ防止方法』と『条例』を十分に理解し、率先して遵守する姿勢を見せることが重要です。さらに、従業員へのカスハラ研修や社内教育を積極的に実施し、カスハラに屈しない企業体制を構築しましょう!
従業員は毅然とした対応を!企業は従業員のフォローを!
その姿勢をもって、顧客の理解と協力を得ましょう!
カスハラ防止のためには、その様な対応力を高めることが求められています。
カスタマーハラスメント研修導入を検討している方へ
心理学の学校「Tree」では、カスハラ対策を中心とした企業研修やセミナーを実施しています。以下のようなニーズにお応えします。
- 従業員向けのメンタルヘルスケアを含むカスハラ対応研修
- クレームとカスハラの見分け方と柔軟な対応方法
- 未然防止策を取り入れた顧客対応マニュアルの策定支援
心理的な側面から顧客対応を見直し、従業員と顧客の両方が安心できる環境を一緒に構築していきましょう。
カスタマーハラスメント研修の導入をご検討されている方は
以下のフォームよりお問い合わせください。