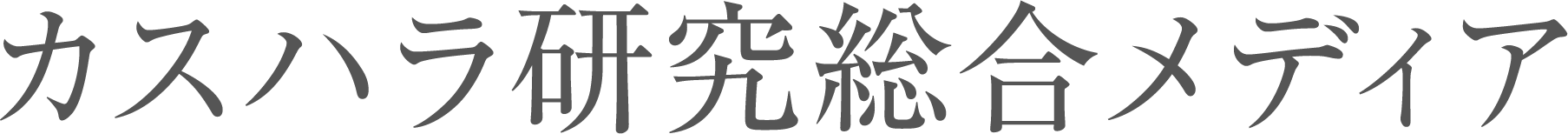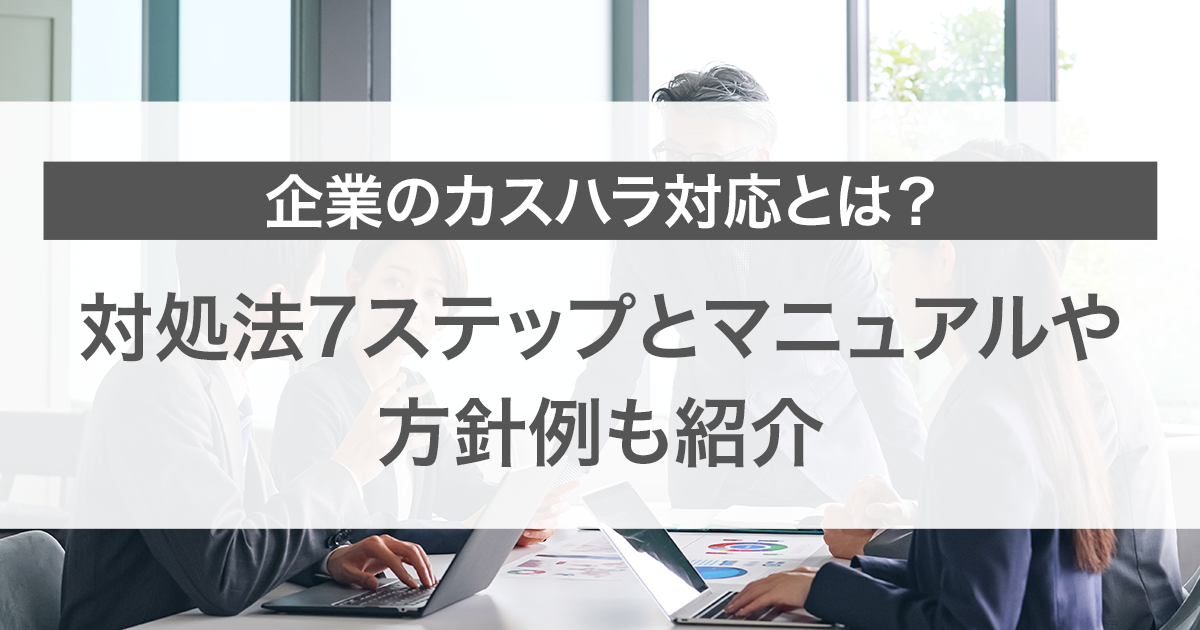「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、悪質なクレームや嫌がらせなど、顧客による迷惑行為のことです。
企業として、カスハラから従業員を守る対応が求められます。
そこで、この記事では、企業や個人のカスハラ対応について解説します。
知っておくと安心な7ステップの対処法や対応のためのポイント、実際に運用されている対応事例なども紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
カスハラ対策の義務化が発表

2024年12月、厚生労働省がすべての企業に対し、カスハラの防止対策を義務付ける方針を発表したことが報じられました。カスハラ防止に向けて、いよいよ政府が動き出すとなれば各企業にも対応が求められます。
労働契約法の第五条にも定められているとおり、企業には従業員の健康と安全に配慮するという「安全配慮義務」があります。たとえカスハラが発生したとしても、会社がしっかりと対応できる体制を整えていることが肝心です。
カスハラと正当なクレームは違う
カスハラには、企業が従業員を守るために断固として立ち向かう必要がありますが、正当なクレームの場合は、顧客の声を受け入れて誠実に向き合わなければなりません。
この判断は難しいものですが、判断基準を設けて事前に理解しておくことが大切です。
カスハラとクレームの違い
クレームが悪質なものでカスハラだと判断するための基準として、下記の観点で考えてみましょう。
① 顧客等の要求内容に妥当性はあるか
② 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲であるか
まずは事実関係と、顧客の主張の根拠や自社の過失の有無を確認します。そのうえで、主張が妥当なものであれば正当な顧客の声として対応します。ただ、正当なクレームであっても、暴言や嫌がらせなどに行為がエスカレートしてカスハラに発展するケースがあるため、慎重な見極めを要します。
警察が対応するレベルのカスハラとは
顧客からの暴行や居座りなどが発生した場合、現場だけでは対応しきれなくなることもあるでしょう。被害の拡大を防ぐためにも警察に介入してもらう判断が必要です。
【カスハラで起こりやすい犯罪と行為】
・脅迫罪(脅し文句や振る舞いで従業員を怖がらせる)
・暴行罪、傷害罪(従業員に暴力を振るう)
・恐喝罪(金品を要求する)
・強要罪(土下座などの義務のない行為を要求する)
・威力業務妨害罪(業務を妨害する)
・不退去罪(居座り続ける)
・名誉毀損罪(会社や従業員の名誉を傷つける)
カスハラが発生!とるべき対応7ステップ
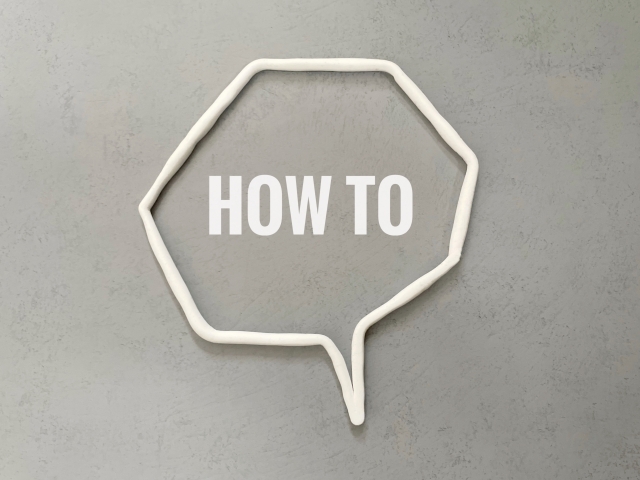
顧客からのクレームがカスハラに該当すると判断した場合、冷静な対応が求められます。適切な手順を踏んで、毅然とした態度でのぞみましょう。
カスハラ発生時にとるべき7ステップの対応を順番に説明します。
【カスハラ発生時にとるべき対応7つのステップ】
①上司・責任者への報告
②顧客の主張を聞き取り、記録
③その場で対応するか、日時や場所をあらためるか判断
④社内で対応方針を決定し、顧客へ通知
⑤被害者のケア
⑥記録・報告書の作成
⑦対応マニュアルを見直し、必要に応じてアップデート
①上司・責任者への報告
現場対応者は、上司や部署の責任者へ報告します。
対応者本人だけの対応や、むやみにその場で終わらせようとせず、状況を報告し共有することで、適切な指示やサポートを受けられる体制になっていることが大切です。
②顧客の主張を聞き取り、記録
状況を正確に把握するため、顧客の主張を聞き取って記録を残します。
相手の誤解が分かった場合は、反論せず落ち着いて正しい情報を伝えます。また、不明な点はこの時点で明らかにしておきます。
初動の事実確認は、その後の対応判断に関わる重要なプロセスなので、丁寧に行いましょう。
記録は、筆記と録音を組み合わせると万全です。録音の同意について、「証拠保全」を目的とする場合は、相手に伝える必要はないとされています。一方で、録音することをあえて相手に伝えると、暴言等のけん制になります。
③その場で対応するか、日時や場所をあらためるかを判断
その場で対話ができ、解決に向かいそうであればそのまま対応を進めます。状況が変わらないと判断した場合は、一旦持ち帰るという選択肢もあります。
クレーム対応の基本に「変える」という方法があります。人を変える、場所を変える、日時を変えるの3つです。状況がリセットされることで、興奮していた心情が落ち着き、あらためて冷静に話し合える可能性が出てきます。
また、リセットする間に、会社側の方針を検討する時間も確保できます。
④社内で対応方針を決定し、顧客へ通知
あらためて対応することになった場合は、社内の指針に沿って対応方針を決定し、後日顧客に伝えます。
対応方針の検討には、専門窓口の担当者や顧問弁護士など社外の専門家にもアドバイザーとして意見をもらい、適正な対応を導き出しましょう。
⑤被害者のケア
被害を受けた従業員のケアは必須です。
精神的な苦痛から、体調やメンタルに不調が起こっている可能性も考えられます。カウンセリングや面談、声掛けを実施するなどの措置を早急にとりましょう。
カスハラをきっかけに休職や離職に追い込まれることは珍しいことではありません。従業員がモチベーションをさげることなく継続して働けるよう配慮しましょう。
⑥記録・報告書の作成
カスハラ発生の事案を記録として残すことや、報告書を作成することも重要です。
経緯や対応プロセスをデータ化しておくことで、今後の資料として役立ちます。防止策の検討にも活用できるので、必ず見える形で保存しましょう。
⑦対応マニュアルを見直し、必要に応じてアップデート
対応マニュアルは、随時見直してアップデートすることが大切です。
想定外のカスハラ事案の発生や、あたらしい業務オペレーションを導入することもあるでしょう。現在のトレンドにあったマニュアルを用意することで、適切に備えることができます。
カスハラ対応の切り返しフレーズ10選

理不尽な言動やクレームを訴えてくる場合、不当な目的を持っていると考えるのが妥当です。安易に謝罪したり要求を受け入れたりするべきではありません。また、共感や曖昧な表現での発言も避け、しっかりと拒否の意思を示すフレーズを使いましょう。
ここぞというときに使えるフレーズを紹介しますので、ぜひ覚えておいてください。
【暴言や強要に対して】
① 「そのようなことはいたしかねます。強要はどうかお控えください。」
② 「これ以上の対応をいたしかねます。おひきとりください。」
③ 「そのような行為は強要罪にあたると理解しております。」
④ 「これ以上そのようなことをなさるなら警察を呼びます。」
⑤ 「これ以上のご無理をおっしゃるようなら弁護士に相談します。」
⑥ 「お怒りの気持ちはよくわかりました。しかしそのような暴言を口にされるのであればこれ以上の対応はできません。」
【金品の要求に対して】
⑦ (誠意を見せろ)「誠意とは、具体的にどのようなことをお望みでしょうか。」
⑧ (ここまでの交通費を払え)「個人のご事情については、対応策がございません。」
【やりとりを終える】
⑨ 「私の判断では回答できませんので、事実関係を確認した上で会社として回答いたします。」
⑩ 「これが当社の誠意を尽くした回答です。これ以上は応じかねます。」
カスハラに適切に対応するためのポイント

ここからは、カスハラに対応する際のポイントを紹介します。
通常のクレームと異なり、行き過ぎると犯罪につながりかねないカスハラ。
対応する側は、冷静かつ慎重に対応することが基本です。
- 複数人数で対応する
- 記録をとる
- むやみに解決を急がない
- 警察や弁護士など外部機関と連携
- 情報を共有し、日頃から対応を練習する
複数人数で対応する
面談の際は、必ず2名以上で対応しましょう。
ひとりで対応するのは精神的な負担が大きいうえ、相手に強い態度に出られる隙を与えます。
複数人数で対応し、話す人、記録係など担当をわけておくと進行がスムーズです。万一に備えて、通報する係と連絡先もあらかじめ決めておくと万全です。
記録をとる
記録をとることは、相手の要望を正確に把握し、論点を整理することに有効です。
主張がずれてきてしまったり、言った言わないなどの水掛け論になったりするのを防ぐことができます。内容の整理と証拠のためにも必ず記録をとりましょう。
むやみに解決を急がない
カスハラに対応する際、解決を急ぐのは禁物です。
相手の態度に焦りを感じたり、早く終わらせたい気持ちになることは当然ですが、焦りや不安によって判断を早まったり謝ったりすることがあるからです。
また、安易に要求を受け入れると、相手に成功体験を与えることになり再発しかねません。
「社内でよく検討して回答する」や、
「コンプライアンスに関わる可能性があるため弁護士にも相談して決定する」などと伝え、会社としての方針を提示するようにしましょう。
警察や弁護士など外部機関と連携
警察や弁護士など外部の専門機関と連携し、解決にあたることも必要です。
話し合いが進まず、カスハラがエスカレートした場合、社内では対応しきれなくなる可能性があります。
「通報する」と伝え、実際に通報してもかまいません。被害を拡大しないために必要な判断です。
また、顧問弁護士に相談し法的措置の手続きをとってもらうこともできます。日頃から情報共有するなどして連携し、外部機関も上手に活用しましょう。
情報を共有し、日頃から対応を練習する
カスハラや、あやうくカスハラに発展しかけた事案は、その情報を社内共有しておくと、以後の対策に役立ちます。さらに実際に起こったカスハラを例に、対応を練習することでいざというときの備えになります。
カスハラの発生は事前に予測ができません。だからこそ、いつでも誰でも対応できるよう準備することは、冷静な対応とストレスの軽減につながります。
カスハラ対応マニュアルで備える
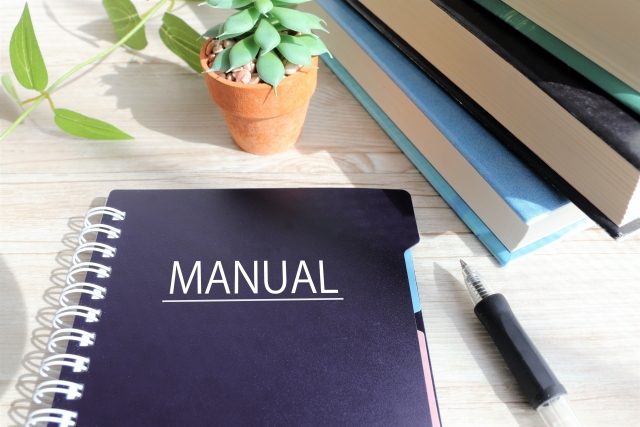
カスハラに適切に対応するために、マニュアルを用意して周知することは大きな備えになります。
2022年に実施された「カスタマー・ハラスメントに関する調査」で、自身または同じ職場の人がカスハラを受けた際の勤務先で、カスハラ対応に関するマニュアルの作成がある(あった)と回答した人は22.1%という結果が出ました。

カスハラの発生事実に対し、対応マニュアルの用意が遅れているのが実状です。
(出典:日本労働組合総連合会「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」)
厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成
2022年、厚生労働省がカスハラ防止対策の一環として「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しました。
企業の自主的な取り組みを促進するためのツールですので、このマニュアルをそのまま活用することはもちろん、参考にして自社の業種に合うように作成するのもよいでしょう。
厚生労働省ホームページでは、マニュアルの他、リーフレットやポスターも用意されていて、ダウンロードが可能です。
(ダウンロードはこちら)
(参考:厚生労働省ホームページ)
自社のカスハラ対応方針の決定と周知
カスハラに適切に対応するには、自社の対応方針を明確にし、従業員に周知しておく必要があります。
カスハラは、企業への要求です。要求に対する姿勢や対応の在り方を、組織の経営陣やトップが従業員に示さなければなりません。
方針の策定には、自社の経営理念や行動指針を踏まえ、組織として従業員を守る姿勢を貫くことが重要です。
【基本方針に含める要素例】
・カスタマーハラスメントの内容
・カスタマーハラスメントは自社にとって重大な問題である
・カスタマーハラスメントを放置しない
・カスタマーハラスメントから従業員を守る
・従業員の人権を尊重する
・常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、周囲に相談してほしい
・カスタマーハラスメントには組織として毅然とした対応をする(引用:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」)
自社の基本方針を公表している企業もあります。公表することで、カスハラの未然防止はもちろん、カスハラに屈しない信念で対策を整えている企業、というイメージアップの訴求にもなります。
【社外に公表している企業例】
高島屋グループ「カスタマーハラスメントに対する基本方針」
NTTドコモ「カスタマーハラスメントに対する基本方針」
ほくほくフィナンシャルグループ「カスタマーハラスメントへの対応に係る基本方針」
自社のカスハラ対応マニュアルの作成と運用
具体的な対応方法や手順を記したカスハラ対応マニュアルを用意しておくと、いざという時に落ち着いて対応ができます。
マニュアルは、自社のカスハラ対応の基本方針をもとに、現場担当者や法務担当部署、顧問弁護士からのアドバイスを参考にして作成します。
従業員がいつでもマニュアルを閲覧できる状態にし、日々の教育や研修に取り入れて活用しましょう。あらたな事例が発生したり、業務体制が変更になったりした際は、マニュアル内容も併せてアップデートしましょう。
【マニュアルに入れるべき項目】 ・発生時のフロー(事実確認、報告、対応、クローズまでの責任の所在と手順) ・事例ごとの対応例 ・事例ごとの望ましくない対応例 ・相談窓口と連絡方法 ・報告書のテンプレート
「カスハラ対応マニュアル」について、こちらの記事で詳しく解説しています!
「厚労省から学ぶ!企業の実務的な【カスハラ対応マニュアル】の必要性と作成手順」
パターン別カスハラ対応の具体例
実際に行われている対応方法や、最新の事例を紹介します。
ぜひ取り組みの参考にしてください。
電話オペレーターを守る「切電」マニュアル
首都高速道路
お客様センターへ寄せられる暴言や要求を繰り返すカスハラ電話を問題視し、不安や恐怖を感じるオペレーターを守るべく「切電マニュアル」の運用を開始。ガイドラインに該当した場合、相手に理由を伝えたうえで電話を切るというもの。運用開始後は、それがきっかけでトラブルに至ったケースはなく、オペレーターの安心感につながっている。
(出典:FNNオンライン)
自治体で働く職員や公務員を守る条例を制定
自治体は組織の特性上、住民にサービスを提供するのが当然だと認識されている場合があり、要求が起こりやすい環境です。
奈良県奈良市
「奈良市法令遵守の推進に関する条例」を施行。条例の整備と併せて、悪質なカスハラを行った対象者の氏名を市のホームページで公開する制度を設けている。
京都府京都市
「市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定。職務を妨げる不正な要望や言動には、市から警告や警察機関への告発を行うこととしてカスハラへの対応方針を示している。
(出典:ジチタイワークスWEB)
AIの活用でクレーム対応ストレスを軽減
NTTコミュニケーションズ
AIを搭載したコールセンター支援システムを開発。顧客と従業員双方の発言を認識し、従業員が見る画面に質問への適切な回答案を表示する。
(出典:産経新聞オンライン)
回答を待たせる時間や、言葉に詰まるストレスを回避できるため、精神的な負担を軽減できる画期的な仕組みだといえます。
カスハラ対応は備えが重要

どの業種でも直面する可能性があるカスハラ。
突然発生するカスハラの影響を最小限にとどめるには、事前の備えが効果的です。
自社の対応方針が明確になると従業員には安心感が生まれます。また、マニュアルを作成し、教育・啓発を継続することで、いざという時のスムーズな対応や再発防止につながります。
従業員教育には、研修を導入するのもおすすめです。
カスタマーハラスメント研修導入を検討している方へ
心理学の学校「Tree」では、カスハラ対策を中心とした企業研修やセミナーを実施しています。以下のようなニーズにお応えします。
- 従業員向けのメンタルヘルスケアを含むカスハラ対応研修
- クレームとカスハラの見分け方と柔軟な対応方法
- 未然防止策を取り入れた顧客対応マニュアルの策定支援
心理的な側面から顧客対応を見直し、従業員と顧客の両方が安心できる環境を一緒に構築していきましょう。
カスタマーハラスメント研修の導入をご検討されている方は
以下のフォームよりお問い合わせください。