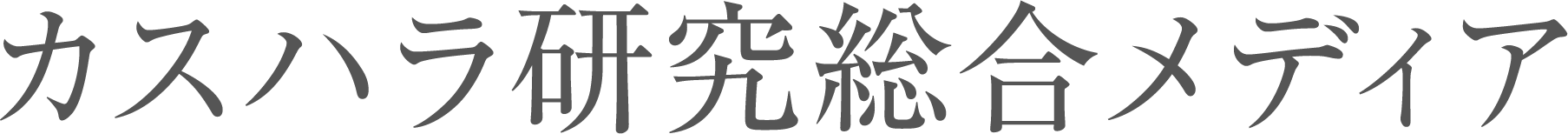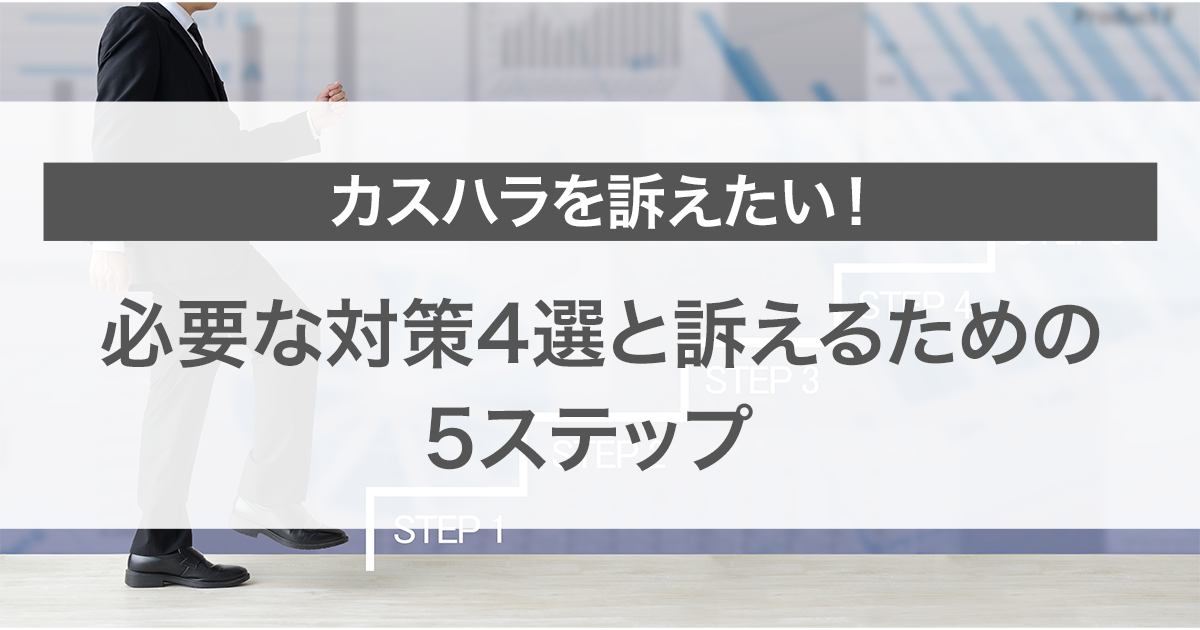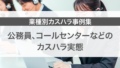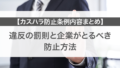「カスハラを訴えることができるのか?」
「カスハラを訴えるのに必要な手順は何か?」
「どのレベルでカスハラと判断してよいのか?」
企業はカスハラから従業員を守る義務があります。
本記事では、上記のような悩みをお持ちの方のために、事案が発生してから落ち着いて対処するために必要な対策と法的手段に訴えるための手順を解説していきます。是非、この記事を参考にしてみてください。
犯罪行為に当たるカスハラ
悪質なカスハラ行為は犯罪に該当することがあります。特に多く見られるカスハラ行為では8つの犯罪行為が該当します。
①威力業務妨害罪
②不退去罪
③脅迫罪
④強要罪
⑤恐喝罪
⑥名誉毀損罪
⑦侮蔑罪
⑧軽犯罪違反
それぞれカスハラ行為に当てはめながら、説明していきます。
威力業務妨害罪
厚生労働省の調査でもカスハラの内容として最も多かった「頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等(72.1%)」に該当する犯罪です。
刑法では「信用毀損及び業務妨害」と併せて以下の通りに明記しています。
刑法223条:
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50年以下の罰金に処する。
刑法234条:
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法の内容から「SNSによる風評被害」や「虚偽の注文により配達させる」などの行為も該当の可能性が高いです。
該当するカスハラ行為は以下の通りです。
・頻繁に来店し、その度にクレームを行う
・度重なる電話
・複数部署にまたがる複数回のクレーム
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
不退去罪
厚生労働省の調査では「拘束的な言動(20%)」に該当する犯罪です。
刑法では以下の通りに明記しています。
刑法130条:
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
飲食店などでの勉強やスマホ、長時間の電話を行っている人に対して注意をしたのにもかかわらず、居座り続けた場合はこちらの罪に当たります。
該当するカスハラ行為は以下の通りです。
・一時間を超える長時間の居座り
・長時間の電話
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
脅迫罪
カスハラの内容として2番目に多かった「威圧的な言動(52.2%)」に該当する犯罪です。
刑法では以下の通りに明記しています。
刑法222条:
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
どのような状況であれ、「火事に気をつけろ」や「自分には暴力団の知り合いがいる」などの発言はこの罪に当たります。
主に該当するカスハラ行為は以下の通りです。
・脅迫的な言動、反社会的な言動
・物を壊す、殺すといった発言による脅し
・SNSやマスコミへの暴露をほのめかした脅し
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
強要罪
「土下座の要求」や「従業員に謝罪文を書かせる行為」などが該当する犯罪です。
厚生労働省の調査では「精神的な攻撃」に当たる行為で44.7%も過去3年間で事案がありました。
刑法では以下のように明記しています。
刑法223条:
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
脅迫罪の内容に加え、他者の権利を侵害する行為により罪が重くなっているところが特徴です。「無償提供しろよ、でないと殺すぞ」や「ネットに流されたくなかったら、土下座しろよ」などの発言はこちらの罪に当たります。
主なカスハラ行為は以下の通りです。
・優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求
・脅迫罪に当たる行為に加え、義務のない行為を強要する
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
恐喝罪
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では「脅迫的な行為」に加えて「正当な理由のない過度な要求」に当たる行為すべてに該当する犯罪です。
刑法では以下のように明記しています。
刑法249条1項:
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法249条2項:
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様にする。
脅迫罪、強要罪と違う点は実際に加害者が利益を得たかどうかです。
例として「SNSで悪評を広めるなどと脅し、不当な慰謝料請求をして実際に慰謝料をもらった場合」がこの罪に適用される可能性があります。
脅迫的な行為に加え、主に以下のカスハラ行為が該当します。
・難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求
・言いがかりよる金銭要求
・契約内容を超えた過度な要求
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
名誉毀損罪
刑法では以下の通りに明記しています。
刑法230条:
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50年以下の罰金に処する。
不特定多数の人が認識できる状況で人の名誉を毀損するような事実を示した場合に成立する犯罪です。「企業や店舗を特定し、犯罪者が経営しているなどとSNSに書き込むこと」や「他の利用者の前で容姿を貶めたり、人格破綻者だなどと罵る発言」などの発言はこちらの罪に適用されます。
主なカスハラ行為は以下の通りです。
・同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める
・一方的にこちらの落ち度に対してのクレーム
・会社、社員の信用を毀損させる行為
・インターネット上の投稿(従業員の氏名公開)
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
侮辱罪
刑法では以下の通りに明記しています。
刑法231条:
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
名誉毀損罪は事実を示して人の名誉を毀損する罪ですが、侮蔑罪に関しては事実が確認できない暴言を吐くことで成立する罪です。従来は拘留または科料のみでしたが、昨今のネット中傷などを受けて厳罰化されました。
主なカスハラ行為は以下の通りです。
・暴言で執拗にオペレーターを責める
・罵声、暴言の繰り返し
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
軽犯罪違反
今まで紹介したものはどれも明らかな犯罪行為でしたが、こちらの罪状に関しては軽微な犯罪に該当する行為です。いたずらとも取れるような行為も含まれていますが、軽犯罪と言っても中には刑法犯として重い処分を科されることもあります。
該当する場合は30日未満の拘留または、1万円未満の徴収です。
主なカスハラ行為は以下の通りです
・店内で大きな声を上げて秩序を乱す
・正当な理由のない業務スペースへの立ち入り
<引用元:厚生労働省ホームページより『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』の10ページ>
カスハラで訴える2つの方法
カスハラで訴訟の手続きを行う場合、民事訴訟と刑事訴訟の2つの方法があります。
それぞれの特徴と必要なものを説明していきます。
民事訴訟
民事訴訟とは個人同士の紛争を解決する裁判手続のことをいいます。
カスハラの場合、以下のような訴えが考えられます。
・カスハラ行為をやめるように行為の差し止めを請求する
・カスハラで要求された内容について対応する義務がないことを確認してもらう(債務不存在確認訴訟など)
・カスハラで生じた損害について損害賠償を請求する(従業員のカスハラ対応で生じた残業代、カスハラで生じた企業の売上減少分など)
<引用元:弁護士法人 S&Nパートナーズ法律会計事務所『カスハラで訴える場合にやっておくべき準備と手順』>
準備すべきもの
・訴状
・客観的な証拠(音声データ、カメラなどの画像データ、来訪した日時や回数、電話の通話記録ややり取りを記録したメモ)
・証拠説明書
・委任状(弁護士に依頼する場合)
・収入印紙
・郵便切手
・送達場所の届出書(必要に応じて)
刑事告訴
刑事告訴とは告訴状を警察に提出し、犯罪の捜査を進めて処罰を求めることです。
被害届は犯罪が起きたことを伝えて捜査を求めるものですが、告訴状はそれに加えて処罰してほしいという意思を示すものになります。
受理されてから捜査が開始され、カスハラが犯罪に当たるとされた場合、カスハラをした顧客等は取り調べを受けるなどして、最終的に刑罰を受けて前科が付く可能性があります。
刑事告訴の場合は以下のような状況によって変わってきます。
・顧客等との関係性
・カスハラの程度
・生じた損害
<引用元:弁護士法人 S&Nパートナーズ法律会計事務所『カスハラで訴える場合にやっておくべき準備と手順』>
準備すべきもの
・訴状
・客観的な証拠(音声データ、カメラなどの画像データ、来訪した日時や回数、電話の通話記録ややり取りを記録したメモ)
・証拠説明書
・委任状(弁護士に依頼する場合)
・収入印紙
・郵便切手
・送達場所の届出書(必要に応じて)
・告訴状
刑事告訴に必要な告訴状の提出は弁護士に相談し、作成を依頼することができます。
どちらの訴訟が解決策に繋がるのかは損害やカスハラの程度などを把握できるものを用意しておき、社内だけで判断するのではなく、弁護士とも相談しながら進めていく必要があります。
企業がカスハラ対策としてやっておくこと4選
カスハラが発生してから対応しようとしても準備をしていなければ、何もできずに見過ごすことになってしまいます。
また、カスハラに関する準備や対策をしていない場合、安全配慮義務違反として被害者(カスハラを受けた従業員)から訴えられる可能性があります。
そういった状況にならないために厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策マニュアル」にある4つの項目
1.カスハラに対する基本方針を示す
2.相談窓口の設置
3.カスハラ対応マニュアルの策定
4.カスハラ研修を行う
から準備・対策を説明していきます。
カスハラに対する基本方針を示す
経営者層がカスハラに対し、従業員を守るという基本方針・基本姿勢を明確にしなかった場合、従業員が相談できない状態や上司がどのような行動を取ればいいのか判断できなくなってしまいます。
point
・経営者がカスハラ対策への取組の基本方針・基本姿勢を明確に示す
・カスハラから組織として従業員を守るという基本方針・基本姿勢、従業員の対応の在り方を従業員に周知・啓発し、教育する。
相談窓口の設置
カスハラを受けた従業員がすぐに相談できるように窓口を設置することが必要です。どこに相談するべきか従業員に対して明確化しておくことで迅速な対応をすることができるようになります。
また、相談者は直属の上司に相談することが多い(社内の上司に相談した:38.2%)と厚生労働省の調査で判明しています。窓口だけではなく、従業員にどのような相談対応をするのか研修を受けさせることも大切です。
point
・相談対応者を決め、相談窓口の設置を行い、従業員に広く周知させる
・担当者だけでなく、同僚からの相談に対応できるように従業員にも研修を受けさせる
カスハラの相談窓口について「カスハラの相談窓口とは?相談先6選と社内の設置についても解説!」の記事で詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。
カスハラ対応マニュアルの策定
実際の現場でマニュアルを策定することによりカスハラへの対応を従業員に身につけさせるだけでなく、今後のカスハラ対応マニュアルを追加することで従業員の安全確保を迅速に行うことができます。
また、従業員が被害を受け、相談を受けた際に状況把握のためにカメラの設置や記録媒体を持たせておくこと、事案が発生時に日時の把握などをマニュアル化することでその後の対応を迅速にすることが可能です。
point
・安全確保のために従業員が対応すべき行動をマニュアル化すること
・日時や現場にいた従業員の把握、記録媒体を持たせることで事案発生時の状況を迅速に把握できるようにすること
カスハラのマニュアルについて「厚生省から学ぶ!企業の実務的な【カスハラ対応マニュアル】の必要性と作成手順」の記事で詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。
カスハラ研修を行う
従業員の身を守るためにマニュアルで策定した後に実際の現場に近い形で研修を行う必要があります。「カスハラとクレームの違いとは何か」「なぜ、このようなマニュアルが策定しているのか」、「どのような行動が安全確保に繋がるのか」を理解することによって従業員は自信をもって行動に移すことができます。
point
・カスハラとクレームの違いを把握させること
・マニュアルに記されている行動でどのような効果が見込めるのか
・身の危険を感じた際の行動を想定させること
カスハラの研修について「企業のカスハラ対応とは?対処法7ステップとマニュアルや方針例も紹介」の記事で詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。
カスハラで訴えるための5ステップ
こちらに悪影響が出た場合、企業は強気に訴える方針を取らなければなりません。
訴えるために必要なものを
STEP1.証拠の収集
STEP2.社内での話し合い
STEP3.弁護士に相談
STEP4.弁護士を通じて交渉する
STEP5.訴訟の手続きを行う
に分けて説明していきます。
証拠の収集
状況把握のためにも、まず必要なのは証拠の収集です。具体的にはカスハラがいつ、どこで、誰によって、誰に対して、どのように、どのくらいされたかを客観的に証明できる証拠があることが望ましいです。具体的には以下のようなものです。
・実際のカスハラの状況を記録したデータ
・カスハラ対応に要した日時や時間の記録
・来訪や電話があった回数や時間帯
・対応した従業員に精神の不調が生じた際の診断書
・現場にいた従業員の聞き取り
こういった証拠を時系列に沿って記録しておくと対応がスムーズになります。
特にカメラなどでの記録は相手を落ち着かせるためにも有効活用することができます。
ただし、顧客が暴力的な行動を取るなど緊急性の高い場合はすぐに警察に連絡し、被害を最小限にとどめることが必要です。
社内での話し合い
本社との連携を取るために集めた証拠や被害を受けた従業員の状況などを把握し、会社内で法的手段に訴えるかどうかを話し合う必要があります。
確認するべき事項として以下の考えがあります。
・正当なクレームかどうか
・被害を受けた従業員の状況
・証拠が客観的かどうか
これらを確認し、法的手段に訴える方針が決まった場合、弁護士に相談することが必要です。
弁護士に相談
社内での話し合いで方針を決めた後、弁護士に相談します。
企業独自で訴訟することも可能ですが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
・カスハラで訴える際に交渉から手続きまでを相談し、任せることができる
・顧客の金銭要求が妥当なのか不当なのか、の判断がつける
・訴えるための負担を軽減することで被害を受けた従業員のケアができる
・その後の注意勧告やマニュアルの改善を行い、即時に明確化できる
・弁護士が対応すると聞いただけで相手が引き下がる可能性を作れる
弁護士を通じて交渉する
弁護士を通じて、カスハラを行った顧客に対して直接交渉を行います。
法律に詳しい弁護士に交渉してもらい、不当な要求に対して「応じないこと」を示すことで相手にも「自分が行った行為は間違いだったのかもしれない」と感じさせることもできます。
訴訟の手続きを行う
相手側が交渉に応じない場合は、民事訴訟か刑事告訴で訴えます。
民事訴訟の場合は、請求する内容の話し合いを行い、集めた証拠を使って勝訴を目指します。
刑事告訴の場合は、民事訴訟で用意するものに加え、告訴状を用意する必要があります。
告訴状は弁護士に作成を依頼することが可能です。
どちらの訴訟が解決策につながるのか、弁護士に相談しながら最適な方法を選ぶことが大切です。
訴訟は、従業員を守るための手段として
企業はカスハラから従業員を守る義務があります。しかし、義務だけでなく、組織としてカスハラに対応する姿勢を見せることで従業員からの信頼やパフォーマンスの低下を防ぐなど企業を守ることにもつながります。
正当なクレームは企業の新たな発展へとつながりますが、カスハラは利益をもたらすことはありません。いくら顧客でも企業の可能性を妨げる行為をした場合には強気に否定することが大切です。
参考文献
厚生労働省
弁護士法人 S&Nパートナーズ法律会計事務所
カスタマーハラスメント研修導入を検討している方へ
心理学の学校「Tree」では、カスハラ対策を中心とした企業研修やセミナーを実施しています。以下のようなニーズにお応えします。
- 従業員向けのメンタルヘルスケアを含むカスハラ対応研修
- クレームとカスハラの見分け方と柔軟な対応方法
- 未然防止策を取り入れた顧客対応マニュアルの策定支援
心理的な側面から顧客対応を見直し、従業員と顧客の両方が安心できる環境を一緒に構築していきましょう。
カスタマーハラスメント研修の導入をご検討されている方は
以下のフォームよりお問い合わせください。